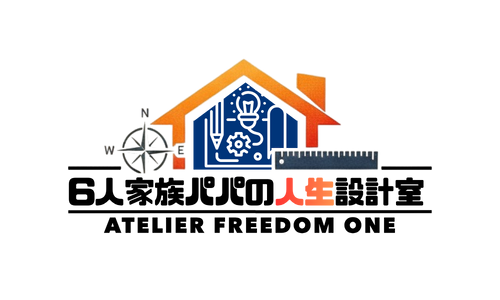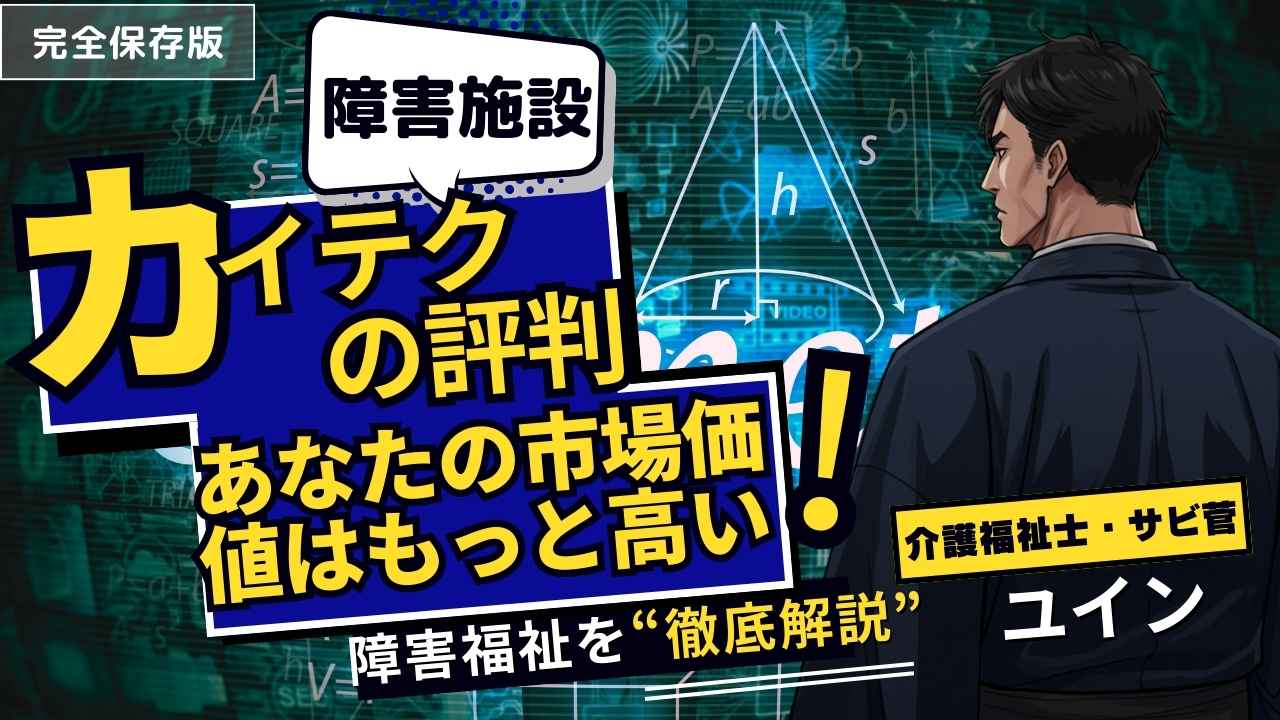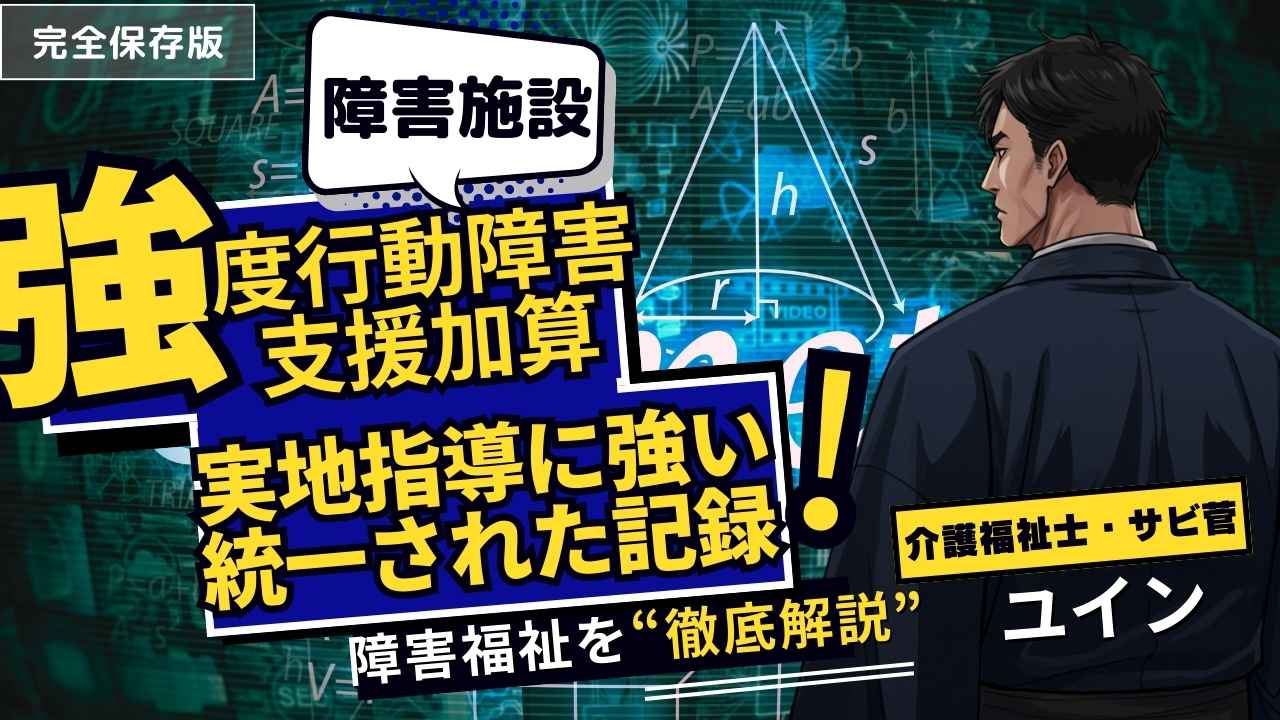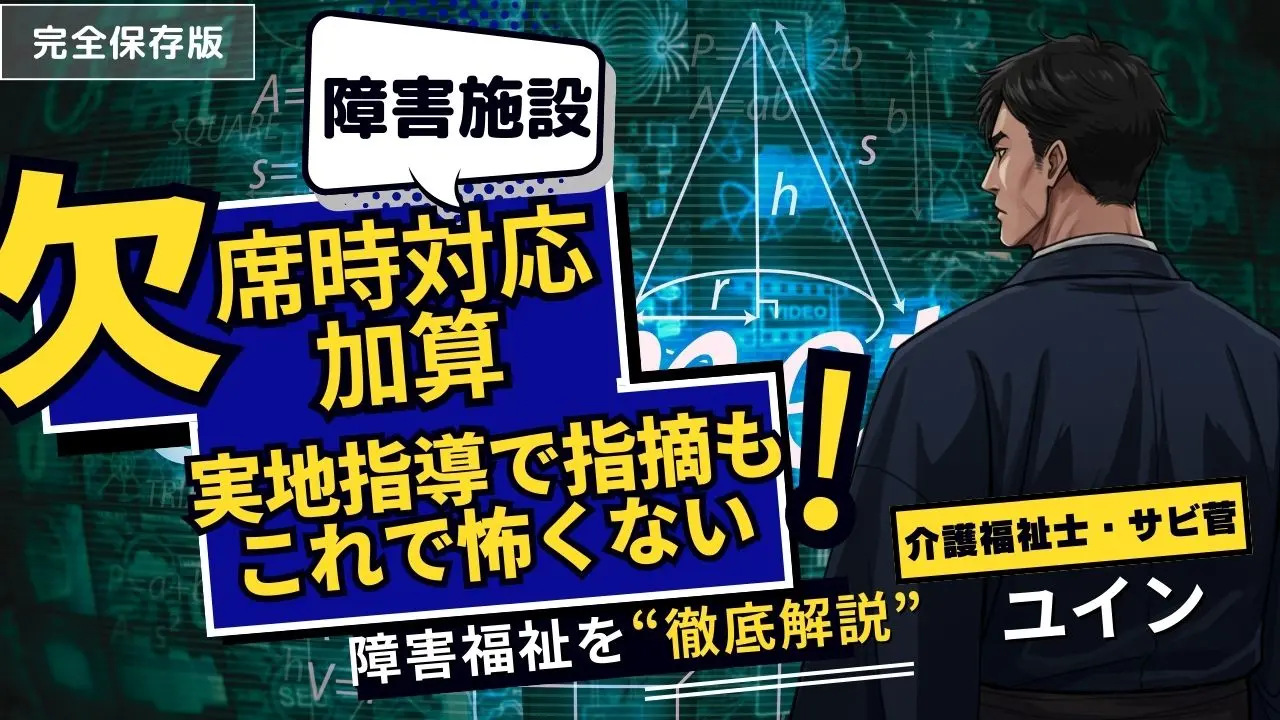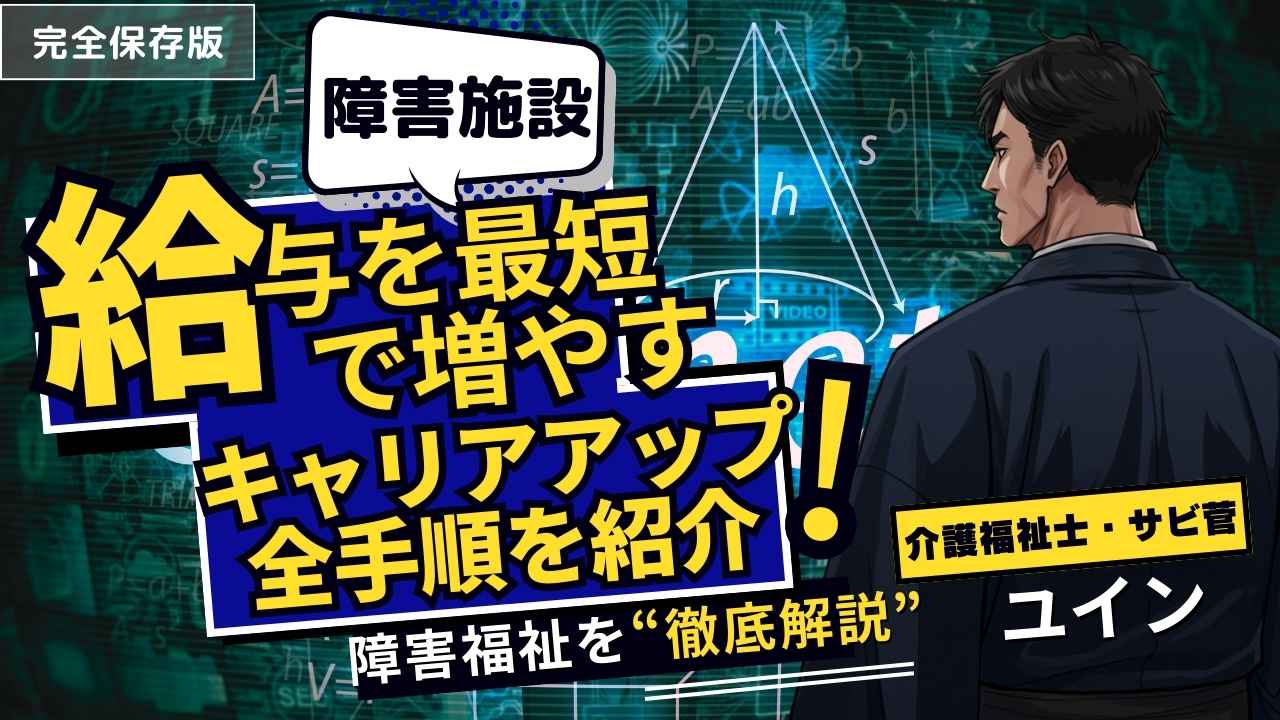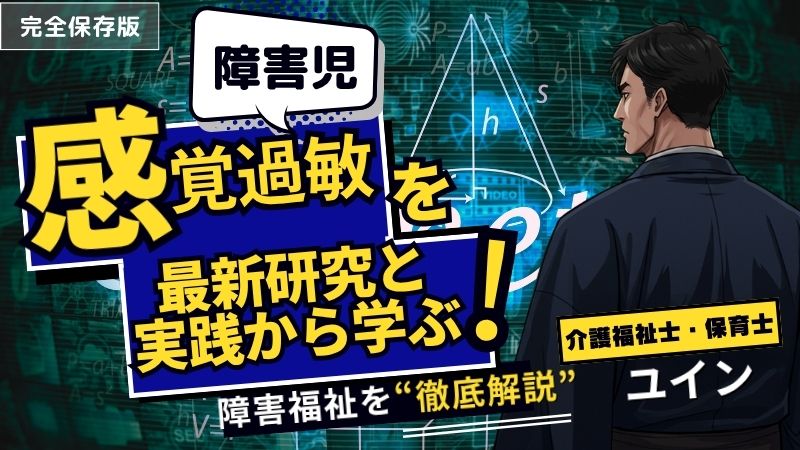障害福祉の「レク」を本気で変えたい支援員へ。海外の視点に学ぶ「挑戦」を引き出す創作活動アイデア集

働く支援員の皆さん、毎日お疲れ様です。
サービス管理責任者(サビ管)や現場リーダーとして、「今日のレク、どうしよう…」「この活動、本当に利用者のためになってるのかな?」と、日々の活動のマンネリ化に悩んでいませんか?
(※私自身のサビ管としての経験上、)利用者の安全を最優先に考えると、活動は「無難」になりがちです。しかし、心のどこかで「もっと利用者の可能性を引き出せるはずだ」という熱意とジレンマを抱えている…そんな方も多いと思います。
この記事は、そんな熱意ある専門職のあなたのための「実践的なヒント集」です。
「海外の最新事例」は、予算も環境も違いすぎて真似できません。
しかし、彼らの「活動に対する考え方(視点)」は、私たちのマンネリを打破する強力なヒントになります。
この記事では、海外の「視点」を、日本の生活介護や放デイの現場で「明日から使える」具体的な活動に落とし込み、さらに厚生労働省や日・米・英の専門機関が示す「根拠」とセットでご紹介します。
なぜ活動がマンネリ化する?「ケア」の視点と「挑戦」の視点

私たち支援者は、利用者の「安全」を第一に考えるあまり、無意識のうちに活動の目的を「安全に時間を過ごしてもらうこと(ケア)」に設定しがちです。
もちろん安全管理は最重要です。しかし、その「安全」が「挑戦する機会」を奪ってしまい、結果として活動が「いつも同じ」マンネリに陥る原因になっていないでしょうか。
海外の先進的な取り組みは、この「活動の目的」そのものが異なります。 彼らは利用者を「ケアされる人」ではなく、「挑戦し、表現する主体」として捉え直しています。
この「視点の転換」こそ、私たちがマンネリを打破する最大のヒントです。
視点①(米国): アートを「リハビリ」から「職業(仕事)」へ
日本の施設でアート活動(創作活動)というと、「リハビリの一環」「余暇活動」「日中活動」と捉えられがちです。
しかし、米国のNPO法人「Creativity Explored(クリエイティビティ・エクスプロード)」は、全く異なる視点を持っています。
- 彼らは「アートセラピー」ではない。 Creativity Exploredは、自らを「臨床的(クリニカル)な実践の場」ではなく、障害のあるアーティストが活動する「ファインアート(純粋芸術)のスタジオ」と位置づけています。指導するスタッフも「セラピスト」ではなく、「プロのアーティスト(Teaching Artists)」です。
- アーティストは「収入」を得る。 ここでの活動は「仕事」です。アーティストは、自分の作品が売れた場合、その収益の50%を受け取ります 。
- 実際に「職業」として成立している。 彼らの作品は、美術館やギャラリーで展示されるだけでなく、CB2(家具・雑貨)やDropbox(IT)といった有名企業にデザインがライセンス供与され、商品化されています 。 Creativity Exploredのアーティストたちは、これまでに総額230万ドル(約3億5千万円以上)もの収入を、自らのアート活動によって稼ぎ出しているのです。
日本の私たちが「工賃」や「リハビリ」と考えている活動を、彼らは「プロのアーティストのキャリア支援」と「ビジネス」として捉えています。
この視点の違いが、活動の質と可能性を根本から変えています。
視点②(英国): 音楽を「技術」から「友情と所属感」へ
音楽活動というと、「上手に演奏する」「リズム感を養う」といった「技術訓練(リハビリ)」の側面を意識しがちです。
しかし、英国の慈善団体「Electric Umbrella(エレクトリック・アンブレラ)」は、「音楽の技術」よりも大切なものに焦点を当てています。
- 目的は「友情」と「所属感」。 彼らのミッションは、学習障害(知的障害)のある人々が、プロのミュージシャンと「共同創造(Co-create)」する場を作ることです。
- 「Musicking(音楽すること)」の重視。 音楽学者クリストファー・スモールが提唱した「Musicking(ミュージッキング)」という概念があります 。これは、音楽を「上手な作品」として鑑賞するだけでなく、演奏、作曲、ダンス、聴くことなど、音楽に関わる全ての「プロセス(活動)」を指します。 Electric Umbrellaの実践は、まさにこの「Musicking」です。上手い下手は関係ありません。全員が「プロセス」に参加することで、孤立しがちな人々が「友情(friendship)」や「コミュニティへの所属感(belonging)」を得ることを最優先の目的としています。
技術の習得(リハビリ)ではなく、音楽というプロセスを通じて「社会的なつながり」を再構築すること。これが彼らの視点です。
視点③(米国): スポーツを「安全な運動」から「”I Can”(私はできる)の精神」へ
日本の施設でスポーツや運動レクを行う際、私たちは「怪我をさせないこと(安全)」を最優先に考えます。その結果、風船バレーや玉入れなど、強度が低く「安全な」活動に偏りがちです。
米国の「National Ability Center(ナショナル・アビリティ・センター、NAC)」は、「安全」の先にある「挑戦」に焦点を当てています。
- ミッションは「I Can(私はできる)」を引き出すこと。 NACは、スキー、ロッククライミング、マウンテンバイク、乗馬など、一見「障害のある人には危険」と思われがちな「アダプティブ・スポーツ(適応型スポーツ)」を提供しています。
- 哲学は「Challenge by Choice(選択による挑戦)」。 彼らの活動の根底には「Challenge by Choice」という哲学があります。これは、参加者自身が「どこまで挑戦するか」を自ら選択することを尊重する考え方です。 支援者は「危ないからダメ」と止めるのではなく、「安全に挑戦できる方法(=アダプティブ)」を準備し、本人が「快適ゾーン(comfort zone)」から一歩踏み出し、「ストレッチゾーン(stretch zone)」へ移行するのをサポートします。
- 「障害」を超えた「可能性」に焦点を当てる。 この「挑戦」を通じて、参加者は「IF I CAN DO THIS, I CAN DO ANYTHING(こんな凄いことができたんだから、私には何でもできる)」という強烈な自己肯定感を得ます 。 NACや同様の団体は、「Beyond Disability(障害を超えて)」という理念を掲げ 、活動を「機能訓練」ではなく、個人の「可能性(potential)」を引き出す「冒険(Adventure)」として捉え直しているのです。
彼らの共通点は、利用者を「守られるべき存在」としてだけ見るのではなく、 「収入を得るアーティスト」 「共に音楽を創る仲間」 「困難に挑戦する冒険家」 として、一人の人間として尊重し、その可能性を信じる「視点」を持っている点です。
この「視点の転換」こそ、私たち日本の支援者が日々のマンネリを打破し、活動の質を劇的に高めるための、最初の一歩となるはずです。
【日本の現場で使える】海外の視点 × 日本の実践アイデア5選

海外の「視点の転換」は、そのまま日本の現場に持ち込めます。 ここでは、日々のマンネリを打ち破る「5つの具体的な実践アイデア」を、支援員の役割の変化や、日本の専門機関の知見と合わせて深く掘り下げます。
アイデア1:【アート】「評価」からの脱却
海外の視点: アートは「うまく描く」ことではなく、「仕事」や「自己表現」の手段。
私たちはつい「上手に描けましたね」と、無意識に作品を「評価」してしまいがちです。
それが利用者の「どうせうまくできない」という諦めや、活動への消極性を生む原因にもなります。
▼ 実践アイデア:「共同制作アート」と「デジタルアート」
- 「巨大!共同制作アート」 床に広げた模造紙やダンボールに、テーマ(例:「海」「宇宙」)だけを提示します。重要なのは、「完成図を決めない」ことです。利用者は「描く」「ちぎる」「貼る」「スタンプを押す」など、自分ができる方法・得意な方法で参加します。
- 「失敗ゼロ!タブレットお絵かき」 施設にあるタブレット(iPad等)に無料のお絵かきアプリを入れます。紙と絵の具と違い、「元に戻す(アンドゥ)」機能が「失敗」の概念を消し去ります。指で色を混ぜる、写真を加工するなど、既存の創作活動では難しかった直感的な表現が可能になります。
【支援員の役割の変化】 支援員の役割は「美術の先生(指導者)」ではありません。利用者の「うまく描きたい」という気持ちと「うまく描けない」という現実のギャップを埋める「環境設定者」です。
- 共同制作では、支援員は「もっと貼って」と指示するのではなく、様々な素材(お花紙、毛糸、シール、梱包材)を手の届く場所に「配置する」ことに徹します。利用者が「これなんだろう?」と手を伸ばした瞬間が、能動的な活動の始まりです。
- デジタルアートでは、支援員は操作を教えるのではなく、一緒に触りながら「こんな色にもなるね!」と「発見を共有する」パートナーになります。
💡参考となる日本の取り組み この「評価しない」アプローチは、日本でも専門的に実践されています。特定非営利活動法人「日本臨床美術協会」は、「臨床美術(クリニカルアート)」を「上手も下手も関係ない」アート活動と定義し、発達障害児の「自尊心・自己肯定感の醸成」にも効果が報告されています。 また、タブレットの活用は「文部科学省」や「国立特別支援教育総合研究所(NISE)」も、特別支援教育におけるICT活用として推進しており、従来の表現方法(筆記など)が困難な児童生徒の「表現の選択肢」を広げる有効な手段とされています。
アイデア2:【音楽】「受動」からの脱却
海外の視点: 音楽は「聴く」ものではなく「積極的に関わる(Musicking)」もの。技術より「友情」や「所属感」が重要。
「音楽レク」と聞くと、利用者が椅子に座って、支援員が流す音楽を「静かに聴く(受動)」か、決まった振り付けのダンスを「受動的に行う」風景を想像しがちです。これでは利用者は「参加者」ではなく「観客」です。
▼ 実践アイデア:「あなたが主役!指揮者レク」
利用者に「指揮者」になってもらいます(指揮棒は新聞紙でOK)。 他の利用者と支援員は「楽器(=声)」になります。「あー」「おー」など、どんな声でも構いません。 指揮者が振る動き(大きく、小さく、早く、遅く、ピタッと止める)に合わせて、全員が声を響かせます。
【支援員の役割の変化】 支援員は「音楽を教える人」から、利用者が「他者を動かす」という能動的な体験をデザインする「演出家」に変わります。
- ポイントは、支援員が「一番大きな声」を出して、恥ずかしがらずに本気で楽しむことです。支援員が「失敗しても面白い」という安全な雰囲気を作ることで、利用者は声(あるいは音)を出すことへの心理的ハードルが下がります。
- 重度の障害があり発声が難しくても、指揮者として「他者を動かす」という「指示(コントロール)」の体験が可能です。これは「やらされる」活動とは真逆の、「自分が中心」となる強力な成功体験です。
💡参考となる日本の取り組み この「参加」と「非言語コミュニケーション」を重視する考え方は、音楽療法の核となるものです。「日本音楽療法学会」は、音楽療法を「音楽の持つ、生理的、心理的、社会的働き」を用いてQOL向上を目指すもの、と定義しています 。技術の上手さではなく、音楽を通じて他者と「つながる」こと、「参加」すること自体に大きな意義があるとしています。
アイデア3:【テクノロジー】「禁止」からの脱却
海外の視点: テクノロジーは「遊び」ではなく「ライフスキルを学ぶ教材」であり、「全員参加」を可能にするツール。
「ゲーム=悪」「YouTube=受動的」と、テクノロジーを活動から遠ざけていないでしょうか。しかし、現代の利用者が日常で触れているツールを「禁止」することは、彼らの興味・関心と支援を切り離すことになります。
▼ 実践アイデア:「ルールを守って『協力』するEスポーツ」
「ゲームは禁止」ではなく、「活動(仕事)として取り組む」という視点で導入します。 (例:マインクラフト、あつまれ どうぶつの森、太鼓の達人、ぷよぷよeスポーツ) 重要なのは「一人で遊ばせる」のではなく、「明確なルール(時間・言葉遣い)のもと、チームで協力して目標を達成する」活動として設計することです。
【支援員の役割の変化】 支援員は「ゲームを監視する人」から、ゲームを「教材」として活用する「SST(ソーシャルスキルトレーニング)のトレーナー」に変わります。
- 「負けた時にどう振る舞うか(感情のコントロール)」「どう言葉をかければ協力してもらえるか(依頼)」「順番をどう守るか(交渉・受容)」といった、日常生活で必ずぶつかる社会的スキルを、ゲームという「安全なシミュレーション環境」で練習できるのです。
- 「どうぶEスポーツ」のように、Microsoftのアダプティブコントローラーなど、身体的なハンディキャップがあっても参加できる機器の導入を検討することも、インクルーシブな環境づくりの一環です。
💡参考となる日本の取り組み ゲーム内のルールを守って協力プレイをすることは、まさにSSTの実践の場となります。「厚生労働省」のポータルサイト「こころの耳」でも、SST(社会生活技能訓練)を「社会適応能力を改善することを目的に行う技法訓練」と定義しています。ゲームという楽しさの中で、日常生活での「適切な対応方法」を具体的に練習できるのです。
アイデア4:【スポーツ】「安全(のみ)」からの脱却
海外の視点: 「安全なケア」から「”I Can”(私はできる)」という「挑戦」へ。
「安全第一」は絶対です。
しかし、「安全=何もしない・させない」になってしまうと、活動はマンネリ化します。風船バレーや玉入れは素晴らしいですが、それ「だけ」になっていませんか?
▼ 実践アイデア:「究極のインクルーシブ・スポーツ『ボッチャ』」
ボッチャを強く推奨する理由は、それが「障害の重軽度や年齢、性別、経験に関わらず、対等に競い合える」ように設計された究極のインクルーシブ・スポーツだからです。 重度の障害があり、ボールを投げられなくても、「ランプ」と呼ばれる滑り台のような補助具(勾配具)を使えば、自らの意思で狙いを定めて参加できます。
【支援員の役割の変化】 支援員は「怪我をさせないように見守る人」から、利用者の「どうせできない」を「どうすればできるか?」に変える「伴走者」に変わります。
- ボッチャの本当の面白さは「戦略性」にあります。体力ではなく「頭脳」が勝敗を分けます。支援員は利用者と一緒に「どうすれば勝てるか」「相手のボールをどう弾くか」を本気で作戦会議する「チームメイト」になります。
- この「できない」を「工夫(補助具)で可能にする」という視点こそ、私たちが目指す「挑戦(I Can)」の支援そのものです。
💡参考となる日本の取り組み ボッチャは、パラリンピックの正式種目であり、「一般社団法人日本ボッチャ協会」は「一緒があたりまえの社会にする」という強力な理念(パーパス)を掲げています。この活動を取り入れること自体が、施設として「インクルーシブ(包摂的)な社会を目指す」というメッセージにもなります。
アイデア5:【演劇】「恥ずかしさ」からの脱却
海外の視点: ドラマ(演劇)は、「失敗を恐れずに」社会的スキルを練習できる安全なリハーサルの場。
「演劇レク」というと、発表会や「お遊戯」を想像し、利用者も支援員も「恥ずかしい」と敬遠しがちです。しかし、演劇の本質は「役を演じる」ことにあります。
▼ 実践アイデア:「日常生活リハーサル(SST)」
これは「演劇」という名のSST(ソーシャルスキルトレーニング)です。「バスに乗る」「コンビニで買い物をする」「病院で受付をする」など、日常生活の具体的な場面を設定します。 そして、支援員が「いつも無愛想なバスの運転手」「レジ袋がいるか聞いてくれないコンビニ店員」などの「ちょっと困った役」を演じます。
【支援員の役割の変化】 支援員は「正しいやり方を教える人」から、利用者が「失敗」を安全に経験できる「リハーサルの相手役」に変わります。
- ポイントは「正しくできなくても良い」と伝えることです。「うまく言えなかった」「どうすればいいか分からなかった」という体験こそが、「じゃあ、次はこう言ってみようか」という「練習」につながります。
- この「役割演技(ロールプレイング)」は、実際の場面でパニックになりがちな利用者にとって、予行演習となり、社会生活での不安を軽減します。
💡参考となる日本の取り組み この「役割演技」は、アイデア3でも触れたSSTの中心的な技法の一つです。 さらに、日本でも「日本ドラマセラピー協会(JADiT)」などが設立されており、「演劇的手法を用いた心理療法」として、SSTをより安全で創造的な形で行う「ドラマセラピー」の有効性が注目されています。
【実践のヒント】施設で「新しい活動」を始めるための「3つの壁」と突破法

「新しい活動、面白そうだ。でも、ウチの施設じゃ無理だよな…」 そう感じていませんか?
熱意を持って「変えたい」と思っても、必ず立ちはだかる「3つの壁」があります。 しかし、その壁は「専門性」と「ちょっとした工夫」で必ず突破できます。
壁その1:「安全管理」という最強の壁
「そんな活動、危ない」「何かあったら誰が責任取るの?」
これは最も手ごわい壁です。「安全第一」という言葉は、福祉現場において絶対的な力を持っています。
しかし、私たち専門職(介護福祉士やサビ管)は、この言葉の「裏側」を冷静に見る必要があります。
【深掘り】リスクマネジメントとは「何もしないこと」ではない
本当のリスクマネジメントとは「リスクをゼロにすること(=挑戦を禁止すること)」ではありません。それは「リスクの放棄」です。 専門職が行うべきは、「リスクを特定し、評価し、管理(コントロール)した上で、挑戦の機会を創出すること」です。
「危ないからやらない」という判断は、利用者の「廃用症候群(身体機能の低下)」や「QOL(生活の質)の低下」「意欲の減退」という、別の重大なリスクを生み出しています。 私たちは、利用者の「転倒するリスク」と、利用者の「挑戦する権利・尊厳」を天秤にかける専門家のはずです。
【突破法:サビ管・リーダーとしての実践】
- 「ヒヤリハット報告書」を「禁止リスト」から「攻略データ」に変える ヒヤリハットや事故報告書を「ほら、やっぱり危ない」という禁止の根拠にしていませんか? それは違います。ヒヤリハットは「どうすれば安全に挑戦できるか?」を分析するための「最高の攻略データ」です。 「Aさんは床の段差でつまずきやすい(データ)」→「だからこそ、段差のないボッチャなら安全に集中できる(実践)」 このように、データを「挑戦のための分析」に使いましょう。
- 「個別支援計画」を「最強の盾」にする サービス管理責任者(サビ管)の最強の武器は「個別支援計画」です。 計画書に「本人の希望:仲間と勝負事を楽しみたい」「支援目標:ボッチャの戦略を立てることで、見通しを立てる力を養う」と、本人のニーズと支援の意図を明記します。 こうすれば、その活動は「ただの遊び」から「計画に基づいた専門的支援」に変わります。万が一の時も、「なぜその活動をしたのか」を説明する最強の盾となるのです。
壁その2:「予算がない」「道具がない」という資源の壁
「ウチは貧乏だから」「そんな高い機材、買えないよ」
これも、新しい提案をすると必ず出てくる「言い訳」の壁です。
【深掘り】最大の資源は「予算」ではなく「支援員の工夫」
海外の事例を見ると、たしかに立派な機材を使っています。
しかし、彼らの本質は「機材」ではなく「アイデア」です。そして、私たち支援員の最大の資源は「予算」ではなく「今あるもので何とかする工夫(創造性)」です。
【突破法:0円から始める「お試し実践」】
- 「0円レク」で実績を作る まずは、お金のかからない活動で「ほら、マンネリが破れた」という小さな成功実績を作ります。
- 指揮者レク(アイデア2): 必要なのは新聞紙1本と、支援員が「本気で楽しむ声」だけです。
- 日常生活リハーサル(アイデア5): 必要なのは、支援員の「ちょっと意地悪なコンビニ店員」を演じる「演技力」だけです。
- 「本物」ではなく「代用品」で試す 「ボッチャをやりたい」と提案して、いきなり公式球(数万円)の予算を申請しても通りません。 「100円ショップのカラーボールで1回だけ試させてください」と提案します。 まずは「もどき」で良いのです。それで利用者が熱狂し、普段見せないような集中力や笑顔を見せたら、どうでしょう? その「写真」こそが、次の会議で「公式球を買うべき理由」を説明する、何よりの証拠(エビデンス)になります。
- 「既存の道具」の「使い方」を変える 「タブレットお絵かき(アイデア1)」も、新しく買う必要はありません。施設に1台はあるはずの、支援員が記録用にしか使っていないタブレットを使います。 「(どうせ使ってない)あれを、週に1時間だけ活動で使わせてほしい」と提案するのです。リソースは「買う」ものではなく「見つける」ものです。
壁その3:「他の職員が乗ってこない」という人間の壁
「私だけが熱くても、周りが冷めてる」「『また何か始めたよ』って目で見られる」
これが、実は最も心を折られる壁かもしれません。
【深掘り】人は「正論」では動かない。「感情(と根拠)」で動く
多忙な同僚に「マンネリはダメだ!海外ではこうだ!」と正論をぶつけても、「忙しいのに、面倒なことを増やすな」と反発されるだけです。 人は「正論」では動きません。人が動くのは、「感情が動いた時」と「納得できる根拠(やる理由)がある時」です。
【突破法:支援員を「巻き込む」専門的提案術】
- 「活動」を提案するな。「課題の解決策」を提案せよ これが、サビ管やリーダーが最も意識すべき点です。
- ダメな提案: 「皆さん、SST(社会生活技能訓練)は大事なので、明日から演劇レクをやります!」 (同僚の反応:は? 忙しいのに。何それ? 恥ずかしい…)良い提案: 「最近、Aさんが『コンビニでうまく話せない』と悩んでいます(課題の共有)。そこで、Aさんの不安を減らすために、私とBさんで『コンビニの店員役』をやるので、Aさんと一緒に『リハーサル(アイデア5)』を試してみませんか? これは厚労省も推奨するSST(役割演技)という専門的な支援です(根拠の提示)」
- 「楽しそう」ではなく「専門性」で語る 「楽しそうだから」は、支援の動機として弱すぎます。 「この活動(ボッチャ)は、日本ボッチャ協会が『一緒があたりまえの社会にする』と掲げるインクルーシブな活動であり、当法人の理念にも合致します」 「この活動(ゲーム)は、SSTの一環であり、利用者の社会的スキル向上という計画目標を達成するために有効です」 このように、この記事で紹介したような「公的な根拠」を使って、「遊び」を「専門的支援」へと翻訳して説明しましょう。
- まずは「戦友」を一人だけ見つける 全員を一度に説得しようとしてはいけません。必ず失敗します。 まずは、あなたの熱意に共感してくれる同僚をたった一人だけ見つけます。その「戦友」と二人で、前述の「0円レク」や「100均ボッチャ」を試します。 そこで生まれた利用者の「見たことない笑顔」や「驚くべき集中力」こそが、他の冷めていた職員の心を動かす、最も強力な「証拠」となるのです。
まとめ
日々の活動のマンネリ化は、支援員の熱意が足りないからではありません。 「安全なケア」という従来の視点に、「挑戦」や「表現」という新しい視点を加えるだけで、活動は劇的に変わります。
大切なのは、高価な機材ではなく、支援員自身が「どうせ無理」の壁を越え、「どうすればできるか?」と楽しんで考えること。
まずは明日、いつもの活動に「指揮者レク」や「ボッチャ(もどき)」など、小さな「挑戦」を加えてみませんか?